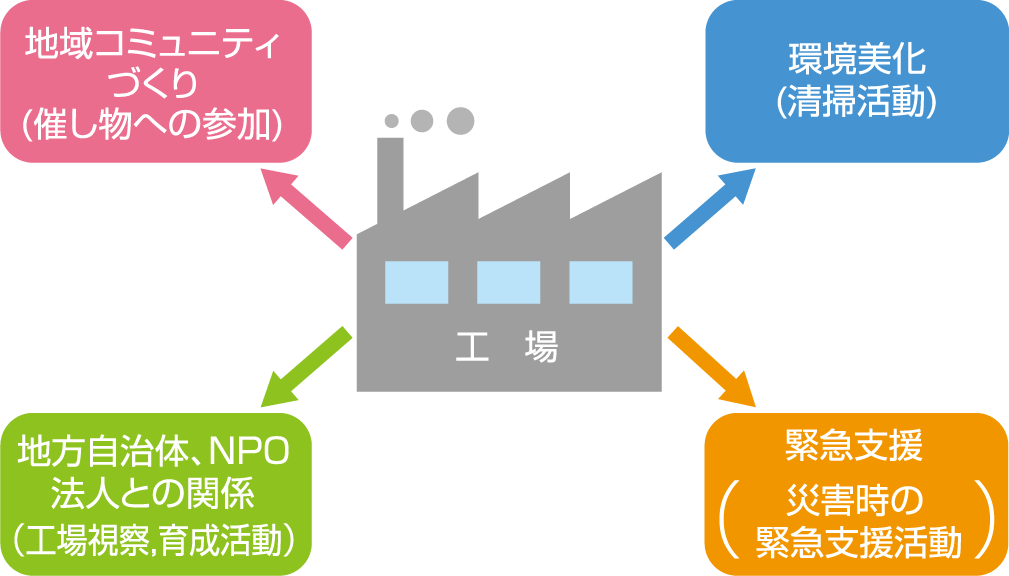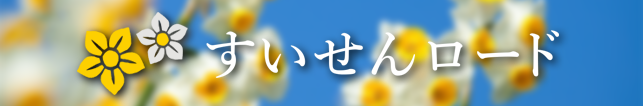社会
社会とともに
ハリマ化成グループは、財団活動などを通じて科学技術の振興、芸術、文化活動の支援や人材育成に取り組んでいます。
また、「地域とともに発展することが企業の使命である」との認識にもとづき、地域の皆様や社員とのよりよい関係づくりを心がけています。
公益財団法人 松籟科学技術振興財団
当社は、創業者である長谷川末吉が1982年に科学技術庁(現 文部科学省)から『科学技術功労者賞』を受賞した栄誉を機に、科学技術の振興と世界文化の発展を願って、1983年3月、財団法人松籟科学技術振興財団を設立しました。以来、科学技術に関する調査・ 研究を対象に研究助成金を贈呈しています。
※松籟(しょうらい)=松の梢に吹く風。また、その音。
設立の趣意
近年、日本の科学技術は、自主技術開発への努力を積み重ね、世界に誇る数多くの技術を創出し、確実な地歩を固めてまいりました。しかしながら科学技術全般に視点を移しますと、とかく成果を期待する余り、応用技術に直接結びつかない研究を軽視する傾向があり、基礎科学の立ち遅れが内外より指摘されております。このような時代の要請を踏まえ、松籟科学技術振興財団は、科学技術に関する調査・研究に対する助成・奨励を行うことにより、科学技術の振興と世界文化の発展に寄与することを目的としています。
研究助成受領者には、
ノーベル化学賞受賞者が2名いらっしゃいます
毎年、優れた研究者に助成金を贈呈しています。そのなかには、野依良治氏と鈴木章氏の、二人のノーベル化学賞受賞者もいらっしゃいます。資源の無い日本にとって科学技術の発展こそが世界に貢献できる道であるとの思いの下、助成する研究の成果に期待しつつ、当財団は今後とも助成、奨励事業を通じて科学技術の発展、振興に貢献してまいります。
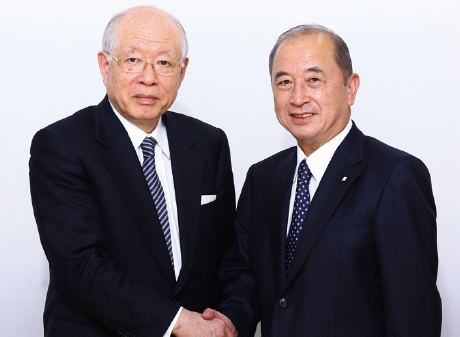
第4回(1986年度)研究助成
2001年ノーベル化学賞受賞
<受賞理由>
キラル触媒による不斉反応の研究

第9回(1991年度)研究助成
2010年ノーベル化学賞受賞
<受賞理由>
有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング
設立:1983年3月
行政庁:内閣府
ホームページはこちら 公益財団法人 松籟科学技術振興財団
公益財団法人 長谷川松籟財団
当社は、創業者である長谷川末吉の、将来を担う若者たちを支援することにより社会の発展に貢献したいとの思いから、2000年3月、財団法人長谷川松籟財団を設立しました。以来、学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な兵庫県出身又は兵庫県内の学校に在学中の高校生及び大学・大学院生の方に、奨学金を給付しています。
設立の趣意
将来の日本を担う学業優秀、品行方正な大学生、高校生が、必ずやその責務を全うされることを期待していますが、十分な援助活動ができないことで経済的理由によって修学を諦めざるを得ない学生がいることは、日本にとっての大きな損失に繋がると考えます。
この様なことから、せめて学生教育に幾分とも役立ちたいと考え、さらに兵庫県における将来の科学技術のさらなる発展に思いを寄せ、経済的理由により修学が困難な兵庫県出身又は兵庫県内の学校に在学中の高校生及び大学生に対して奨学金の給付を行うことによって、今後の科学技術の振興に微力ながらも貢献しようと考え当財団を設立しました。
設立:2000年3月
行政庁:内閣府
ホームページはこちら 公益財団法人 長谷川松籟財団
良き企業市民として
ハリマ化成グループでは、それぞれの事業所が地域の一員として、さまざまな社会貢献活動を行っています。良き企業市民として、従業員一人ひとりが社会貢献活動を支援しています。
次世代の育成や工場見学、清掃活動などの取り組みを通じて、地域の方々との相互理解を深めていきます。